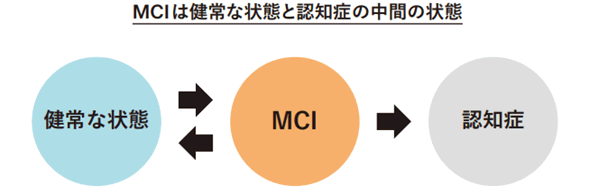退職後の健康管理について
退職後の健康診断等について
退職すると会社や健保組合から毎年きていた健康診断やがん検診の案内がなくなり、自ら情報を集め、健康管理をしていく必要があります。
ご自身とご家族の健康のために、1年に1度の健康診断は継続し、受診が必要だと判断された場合は、なるべく早く医療機関で適切な治療を受けましょう。
退職後の状況によって、活用できるサービスは異なりますので、下記をご確認ください。
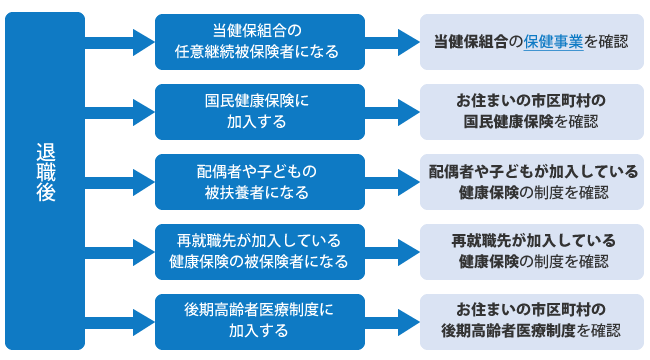
自治体のがん検診について
お住まいの自治体(市区町村)では「健康増進法」に基づいてがん検診を実施しており、ほとんどの自治体で無料もしくは一部の負担金でがん検診を受けることができます。
対象者や検診方法、自己負担額等は自治体によって異なりますので、自治体から送られてくるご案内やホームページ、広報誌等をご確認ください。
悪性新生物、いわゆる「がん」は死因別死亡率が最も高い疾患です。
原因としてはウイルスや遺伝の他、喫煙(受動を含む)や塩分・脂質・飲酒過多、運動不足などの生活習慣が深く関係しているといわれています。
がん検診を受けて早期発見・適切な治療に努めるだけでなく、生活習慣の改善を引き続き心がけることが重要です。
年齢毎に変化する健康課題
平均寿命が延伸している一方で、生き生きと自立して生活できる「健康寿命」との間には10年ほどの差があるといわれています。
ますます長くなる退職後の過ごし方が10年、20年後の生活に大きく影響します。
年齢毎に変化する健康課題を意識しましょう。
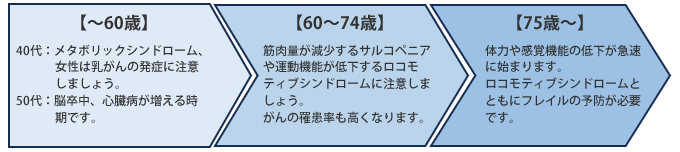
- *1 メタボリックシンドローム:内臓脂肪に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、脳卒中や心臓病などのリスクが増す状態。
- *2 サルコペニア:加齢に伴い、筋肉の量が減少していく現象。25~30歳ごろから進行が始まり、 生涯を通じて進行する。
- *3 フレイル:身体的脆弱性などの影響により、生活機能が障害され、精神心理的脆弱性などが出現し、自律障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスクな状態。
退職後に気を付けたい健康課題
①循環器疾患
脳卒中・心臓病などの循環器疾患は、死亡や介護を要する状態となる主な要因ですが、生活習慣の改善による予防が非常に効果的です。
退職後は、ライフスタイルを変えるよいチャンスです。ウォーキングなど積極的に体を動かし、栄養バランスのとれた食事をゆっくり楽しみましょう。また、地域のイベントや趣味活動に参加して自分なりの楽しみを持つなど、心と体を健康に保つ生活に変えていきましょう。
②ロコモティブシンドローム
運動器の障害をきっかけに日常生活の自立度が低下し、要介護の状態や要介護のリスクが高まる状態のことを指します。
下記ロコチェックでひとつでも当てはまれば、ロコモティブシンドロームの心配があります。ロコモティブシンドロームは回復可能であることが最大の特徴です。可能な範囲で運動習慣を持ち、今ある筋力を保つことが大切です。
運動できない原因となっている痛みや症状がある場合には、専門機関へ相談しましょう。
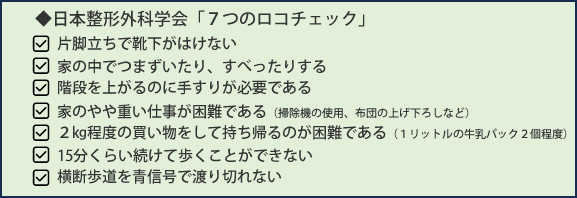
③認知機能の低下
加齢に伴って、物忘れはよくあることかもしれません。しかし、「加齢による物忘れ」と「認知症」は異なります。
例えば「昼食に何を食べたかを忘れる」「人の名前が出てこない」など、体験したことの一部を忘れたが、忘れたことを自覚しているのが加齢による物忘れです。対して、「昼食を食べたこと自体を忘れる」「数分前のことが思い出せない」など、体験そのものを忘れ、忘れた自覚がない場合には加齢によるもの以上の認知機能の低下「認知症」が疑われます。
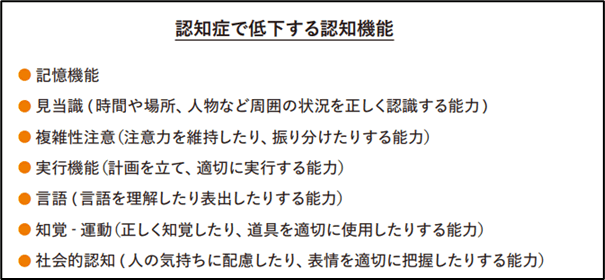
また同時に、焦燥・興奮、暴言や暴力、徘徊などの行動面の症状や、抑うつ、不安、妄想、幻覚、意欲の低下などの心理症状が生じる場合もあります。
認知症とよく似た状態(うつ、せん妄)や、認知症の状態を引き起こす体の病気も様々あるため(甲状腺機能低下症など)、早期に適切な診断を受けることが大切です。
認知症と完全に診断される一歩手前の状態をMCI(Mild Cognitive Impairment:軽度認知障害)といいます。
MCIを放っておくと認知症に進行しますが、生活習慣病のコントロール状況や運動、食事、周囲とのコミュニケーションなど適切な予防をすることで健常な状態に戻る可能性もあります。